早期退職を検討するにあたって、退職金の税金について色々調べたのでまとめてみました。
さらに、細かく見ていくと、所得税には所得税と復興特別所得税の二つがあります。
復興特別所得税とは
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
引用元:国税庁ホームページ
となっており、2037年12月31日まで課税されます。
住民税の方は、普段はあまり意識していないと思いますが、都道府県民税と市町村民税(特別区民税)の二つに分かれています。
それでは、各々の税額の計算方法について説明します。
課税退職所得金額とは、退職金から退職所得控除額を差し引いた額に0.5を掛けた(つまり半分)金額になります。
所得税も住民税もこの課税退職所得金額に対して課税されることになり、この課税退職所得金額が少ないほど課税額が少なくなります。
退職所得控除額の算出方法ですが
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、切り上げ。(1日でも切り上げです)
注2:計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円。
注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額。
つまり、勤続20年までは1年毎に40万円。21年目からは1年毎に70万円ずつ控除額が増えることになります。退職金なので長期勤続が優遇されています。
勤続年数1~40年までの退職所得控除額の一覧を作成しました。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 80万円 | 21年 | 870万円 |
| 2年 | 80万円 | 22年 | 940万円 |
| 3年 | 120万円 | 23年 | 1010万円 |
| 4年 | 160万円 | 24年 | 1080万円 |
| 5年 | 200万円 | 25年 | 1150万円 |
| 6年 | 240万円 | 26年 | 1220万円 |
| 7年 | 280万円 | 27年 | 1290万円 |
| 8年 | 320万円 | 28年 | 1360万円 |
| 9年 | 360万円 | 29年 | 1430万円 |
| 10年 | 400万円 | 30年 | 1500万円 |
| 11年 | 440万円 | 31年 | 1570万円 |
| 12年 | 480万円 | 32年 | 1640万円 |
| 13年 | 520万円 | 33年 | 1710万円 |
| 14年 | 560万円 | 34年 | 1780万円 |
| 15年 | 600万円 | 35年 | 1850万円 |
| 16年 | 640万円 | 36年 | 1920万円 |
| 17年 | 680万円 | 37年 | 1990万円 |
| 18年 | 720万円 | 38年 | 2060万円 |
| 19年 | 760万円 | 39年 | 2130万円 |
| 20年 | 800万円 | 40年 | 2200万円 |
例1)勤続33年で退職金が1,000万円の場合
退職所得控除額は
800万 + (70万 × (33 - 20)) = 1,710万円
退職金よりも退職所得控除額の方が多いので全額非課税になります。
例2)勤続33年で退職金が2,000万円の場合
退職所得控除額は
800万 + (70万 × (33 - 20)) = 1,710万円
課税退職所得金額は
(2,000万 - 1710万) × 0.5 = 145万円
になります。
例3)勤続33年で退職金が3,000万円の場合
退職所得控除額は
800万 + (70万 × (33 - 20)) = 1,710万円
課税退職所得金額は
(3,000万 - 1710万) × 0.5 = 645万円
になります。
この課税退職所得金額を元に税額を求めていきます。
税率の算出は以下の表から税額と控除額を求めます
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例1)課税退職所得金額が1,450,000円の場合
表から税率と控除額を求めて、税率は5%、控除額は0円なので
1,450,000円 × 0.05 - 0円 = 72,500円
になります。
例2)課税退職所得金額が6,450,000円の場合
表から税率と控除額を求めて、税率は20%、控除額は427,500円なので
6,450,000円 × 0.2 - 427,500円 = 862,500円
になります。
この所得税額の事を基準所得税額とも言い、この税額をもとに復興特別所得税を求めます。
例1)所得税額(基準所得税額)72,500円の場合
税率は2.1%なので
72,500円 × 0.021 = 1,522.5円(1円未満の端数は切り捨て)
になります。
例2)課税退職所得金額が862,500円の場合
税率は2.1%なので
862,500円 × 0.021 = 18,112.5円(1円未満の端数は切り捨て)
になります。
ということで、所得税は
例1)勤続33年で退職金が1,000万円の場合
退職金よりも退職所得控除額の方が多いので全額非課税。
例2)勤続33年で退職金が2,000万円の場合
72,500円 + 1,522円 = 74,022円
になります。
例3)勤続33年で退職金が3,000万円の場合
862,500円 + 18,112円 = 880,612円
になります。
都道府県民税 = 課税退職所得金額 × 4%(都道府県税率)
市町村民税(特別区民税) = 課税退職所得金額 × 6%(市区町村税率)
住民税は、都道府県民税と市町村民税を合算したものです。
税率は都道府県民税が4%、市町村民税が6%です。
ほとんどの自治体の税率は同じです。ごくまれに違う自治体があるようです、大きな違いはないですが、正確な金額を把握したい場合には確認してみてください。
単純に住民税の合計が知りたい場合には、課税退職所得金額に10%を掛ければ住民税がわかります。
例1)課税退職所得金額が1,450,000円の場合
都道府県民税の税率は4%、市町村民税の税率は6%
1,450,000円 × 0.04 = 58,000円(都道府県民税)
1,450,000円 × 0.06 = 87,000円(市町村民税)
58,000円 + 87,000円 = 145,000円(住民税)
になります。
例2)課税退職所得金額が6,450,000円の場合
都道府県民税の税率は4%、市町村民税の税率は6%
6,450,000円 × 0.04 = 258,000円(都道府県民税)
6,450,000円 × 0.06 = 387,000円(市町村民税)
258,000円 + 387,000円 = 645,000円(住民税)
になります。
最終的な退職金の手取り額ですが
例1)勤続33年で退職金が10,000,000円の場合
退職金よりも退職所得控除額の方が多いので全額非課税になり10,000,000円。
例2)勤続33年で退職金が20,000,000円の場合
退職金手取り額は
20,000,000円 - 72,500円 - 1,522円 - 145,000円 = 19,780,978円
例3)勤続33年で退職金が30,000,000円の場合
退職所得控除額は
30,000,000円 - 862,500円 - 18,112円 - 645,000円 = 28,474,388円

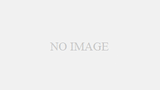
コメント